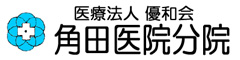- HOME
- 百日咳
百日咳
百日咳とは
百日咳の特徴
百日咳(ひゃくにちぜき)は、Bordetella pertussisという細菌によって引き起こされる、感染力の強い呼吸器の感染症です。特に乳幼児にとっては重篤化しやすく、注意が必要な病気です。その名の通り、咳が長引くことが特徴で、数週間から数ヶ月にわたり発作的な咳が続く場合があります。
乳児期にワクチンの定期接種に組み込まれていますが、10年程度で効果が減弱するため、小学校高学年から高校生にかけての発症が多くみられます。また、近年は成人の発症も増加傾向にあります。
百日咳の原因|細菌の種類と感染経路
原因となる細菌
百日咳の原因菌は「ボルデテラ・パータシス(Bordetella pertussis)」です。この細菌が気道に感染し、咳や気管支の炎症を引き起こします。
感染経路、感染性について
百日咳は飛沫感染によって広がります。感染者が咳やくしゃみをすることで、空気中に細菌が放出され、周囲の人の上気道(鼻やのど)、気管支、肺などに感染します。
患者さんにお話しを聞いてみると、多くの場合、まわりに咳をはげしくしている人がいることが多いです。
感染性は症状の出はじめから2週間程度がいちばん強いです。その後3週間程度経過すると咳が出ていたとしても感染性はなくなるとされています。
潜伏期間と発症のメカニズム
潜伏期間は通常7〜10日ほどです。初期は軽い風邪のような症状ですが、次第に激しい咳へと進行します。
百日咳の主な症状と経過
初期症状(カゼに似た症状):カタル期
鼻水、くしゃみ、微熱などカゼに似た症状から始まります。この段階ではカゼと区別はつかず、百日咳とは気づきにくいのが特徴です。
特徴的な咳(発作性咳嗽・吸気性笛声音):発作期
連続的に短く強い咳(スタッカート)の発作が繰り返され、息を吸うときに「ヒュー」という音(吸気性笛声音)がするのが典型的な症状です。咳のあとに嘔吐してしまうこともあります。夜間眠れないことも多く、患者さんにとって非常に苦しい時期となります。
人によっては2〜3か月持続するとされています。
回復期
激しい咳の症状が1〜2週間かけて徐々に軽快していく期間を経て治癒します。
百日咳の検査と診断方法
問診と臨床症状
前述のような長引く咳や特徴的な音を伴う咳などから疑われます。ほとんどの場合、聴診では異常は認めません。
胸部X線写真や胸部CT
ほとんどの場合、異常な陰影は認めません。
血液検査・PCR検査・培養検査
鼻咽頭ぬぐい液の抗原検査、PCR検査、LAMP法、細菌培養検査で百日咳菌を同定すれば、確定診断になります。また血液検査で百日咳の抗体(PT-IgG抗体)を調べて確定診断する方法もあります。
前者の百日咳菌を同定する検査は精度(感度)が若干低く、百日咳になっていたとしても陰性という結果になってしまうことがある点、後者の血液検査では感染して時間が経たないと陽性にならない点が欠点で、初回の値によってはペア血清といって、日にちをあけて2回目の血液検査をしなければいけないこともあります。
当院では主にLAMP法や血清検査を用いて診断しています。抗原検査は特に感度が十分でない(見逃しやすい)ため、当院では実施していません。いずれも院外の大きな検査会社に依頼するため3-4日結果が出るのにかかってしまいます。発症2-3週間以内であればLAMP法。それ以降であれば血清検査を行うことが多いですが、それぞれの患者さまが鼻咽頭検査、血液検査のどちらを希望されるかも踏まえて判断しています。
どの診療科を受診すべきか?
まずは内科または小児科を受診しましょう。症状をしっかり伝えることが重要です。
百日咳の治療法と自宅でのケア
抗生物質(マクロライド系)の効果と注意点
主にマクロライド系抗生物質(クラリスロマイシンやアジスロマイシンなど)が使用され、初期段階では特に有効とされています。
他者への感染性を減らす効果はありますが、咳症状が著明に改善するわけではありません。
咳のケアと日常生活での対処法
加湿・安静・水分補給を心がけましょう。
入院が必要なケースとは?
乳児や重症化した場合、呼吸困難や無呼吸発作の恐れがあるため、入院治療が必要になります。
百日咳の予防法|ワクチンと感染対策
定期予防接種の重要性
百日咳のワクチンは定期接種の5種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風、ポリオ、ヒブ混合)に含まれています。生後2か月以降に受けることが推奨されています。
ワクチンの副反応と接種時期
副反応はほかのワクチンと比較して特別多いわけではありませんが、接種後の体調変化には注意が必要です。かかりつけの医師と相談のうえ進めましょう。
家庭内感染を防ぐためのポイント
感染者との接触を避け、マスク・手洗い・換気など基本的な感染対策を徹底しましょう。
百日咳かな?と思ったら|受診の目安と注意点
医療機関を受診するタイミング
咳が1週間以上続く場合、激しい咳の場合、音が特徴的な場合などは早めに受診しましょう。
まわりに百日咳が流行している場合は特に注意が必要です。
受診時に伝えるべき症状と経過
咳の開始時期、頻度、音の特徴、家族や周囲での流行の有無などを伝えると診断に役立ちますが、医師や看護師が問診しますのでその場で聞かれたことに答えていただければ大丈夫です。
感染拡大を防ぐ行動とは?
症状がある間は外出を控え、咳エチケットやマスクを着用するなど、周囲への配慮が大切です。
出席停止の基準として
- 特有の咳が消失するまで
- 適切な抗菌薬治療を5日間実施した後まで
とされています。
百日咳の注意点
診断のむずかしさ
百日咳のカタル期はカゼと鑑別がむずかしく、発作期は咳優位型喘息(咳喘息)をはじめとした慢性咳嗽をきたす疾患との鑑別がむずかしいです。さらに病原体を同定する検査(培養、抗原、LAMP法)も精度(感度)がそれほど高くありません。血清診断も発症して時間が経ってからでないと確定に至らないことも多々あります。
特に鑑別となるカゼや咳優位型喘息は非常にありふれた疾患であるため、百日咳の非流行期の場合、呼吸器の専門医であったとしても診断に難渋してしまうことがあります。
咳症状を改善させることのむずかしさ
いざ百日咳と診断されても、抗菌薬治療で咳が速やかに改善するわけではありません。咳症状に関しては鎮咳薬による対症療法になります。しかし薬が効きづらく治療に難渋することが多く、結果的に自宅療養で自然治癒を待つ形になります。
見逃されやすい大人の症状
大人では軽度な咳が続くのみで終わることもあり、カゼと誤認されることも多いです。
子どもや赤ちゃんへの感染リスク
大人からワクチン未接種の乳児へ感染させてしまうケースもあり、特に重症化のリスクが高く注意が必要です。
まとめ
百日咳はかかってしまうと、長期間咳が続いてしまい、治療にも難渋します。そのため、やはりワクチンで予防することが一番重要なことになります。定期接種は確実に接種いただき、最後にワクチンを接種してから10年程度経過している方はワクチンの再接種もご検討いただければ幸いです。